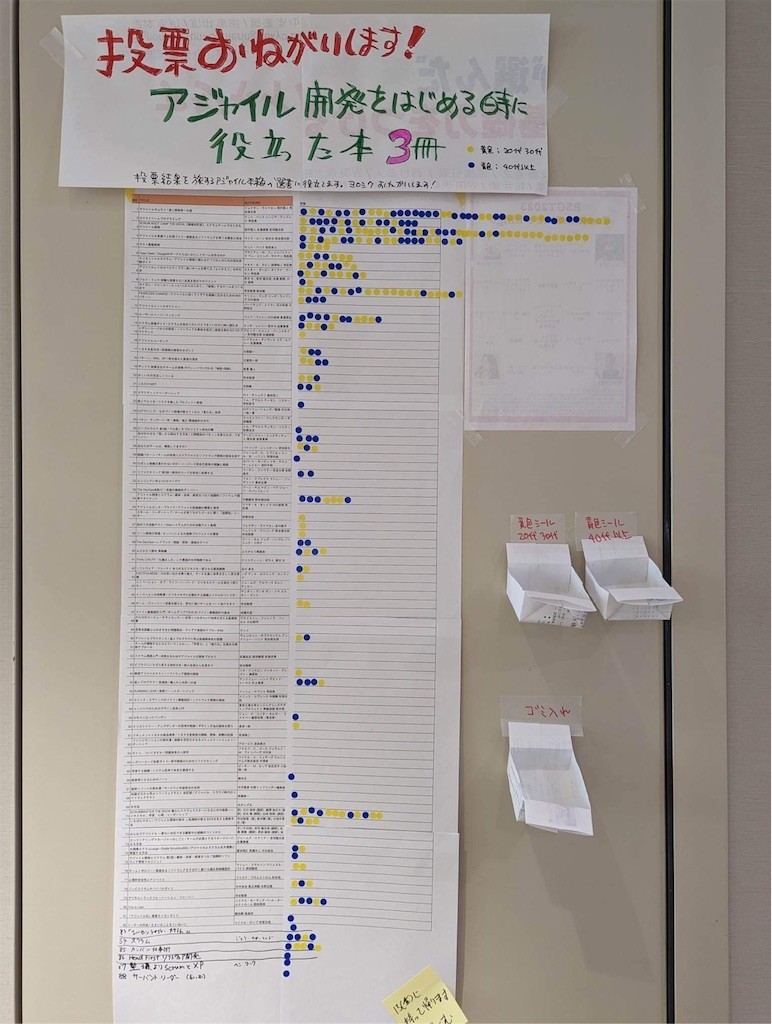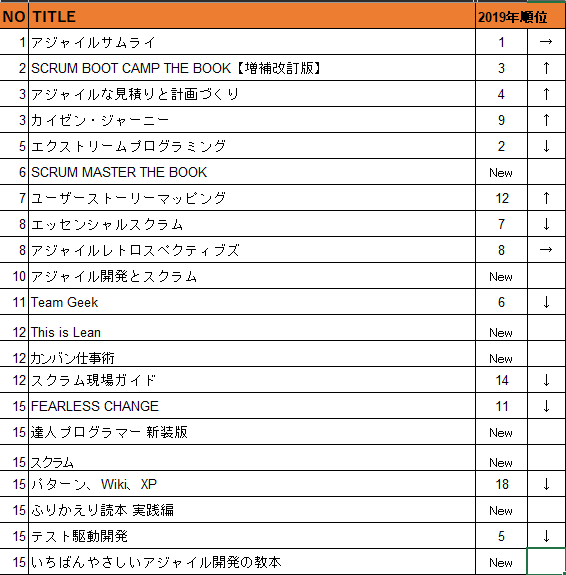読書再開して2ヶ月目。今のところ、YouTubeを見る時間とゲームをやる時間を少し減らして、本を読めてます。
さて、2024年2月に読んだ本たちを紹介します。
世界一流エンジニアの思考法
積読していた、牛尾さんの本を、読んでみました。
・牛尾さんの面白い語り口で、みっちりと、マイクロソフト本社でプログラマーとして結果を出すために、周りの方から受け取ったことが書かれている
・日本のあちこちで行われているであろう、悪しき思考法や、慣習を変えるためのノウハウに散りばめられていた
・牛尾さんがなんでこの本を書こうと思ったかが胸に刺さったので、引用します
海外チームにいて感じる日本の会社との一番大きな違いは、「不幸そうな人がいない」ということだ。みんな楽しそうに、人生と仕事をエンジョイしている。どうやったら自分の人生が幸せになるかを主体的に考えて、仕事の仕方を「選択」している。
牛尾 剛. 世界一流エンジニアの思考法 (文春e-book) (pp.239-240). 文藝春秋. Kindle 版.
海外で経験している「幸せを感じられるような働き方」が日本でもっと広まってほしい、「仕事を楽しい」と思える人が一人でも多く増えてほしい、そんな思いからこの企画を引き受けることにした。
正直、マイクソフト本社と、日本の企業との対比が、読んでてちょっとつらいところもあったのですが、後半出てくるこれらの文章たちを読んで腹落ちしました。
楽しく、幸せに人生と仕事をエンジョイする人を増やすために、牛尾さんがこの本を書いてくれたんだなと思うと、この現実とノウハウを、ITエンジニアに限らず沢山の人に感じて欲しいと思いました。
亡命者
この本は、1995年12月に発売され、長らく絶版だった後、2022年5月に文庫とKindleで再販されたようです。本当に嬉しいことです。
・受け売りですが、第2次世界大戦後、カトリックにおいて革新的な活動は、フランスから発信されることが多かったそう
・著者 高橋たか子さんも、1980年にフランスにわたり、パリで暮らしながら、観想生活を数年間行ったそう(Wikipediaより)
・観想生活は、静かに自らの内面に深く沈思し、故人や神や自分の信じる信仰における絶対的な存在と触れ合い、故人への思いや人生、生きることの意味について思いをめぐらす行為
・この本は、観想生活そのものを小説にしたもの
・読んでいると、当時のフランスのカトリック感や、都市の中に暮らしながら観想生活に導かれていく人達の心の葛藤が興味深く描かれいる。エスプリ(死語かもw)が効いた文章がお好きな方はハマるかもしれません。
・カトリックの有名な聖歌、Salver Materのそもそものラテン語の歌詞の意味が、日本語訳と違っていることを気づかせてもらいました。この本の登場人物いわく「創世記のイブがりんごを食べて、土地を追放されてから、わたしたちは亡命者となり死んで天国に行くことで帰ることができるということ。それをマリア様がイエス様にとりなしてくれるのだ」ということ。
少なくとも私は聞いたことのない解釈で、とても興味深かったです。
組織を変える5つの対話
わたしは、CREATIONLINE MEETUPというイベントを月1回程度、クリエーションラインさんからの依頼で開催させていただいてます。
2/27に、まだ世に出ていない、発売前の『組織を変える 5つの対話』のABD読書会を、訳者の協力の下開催しました。
参加者の方がそれぞれまとめてくださった要約をお聞きすると、この本はとても対話の不安を払拭する、信頼を得る、、、などの工夫をわかりやすく書いてある本のようでした。
まだ本が到着していないのですが、個人的には、不安をどう乗り越えるのかを丁寧に書いている章を、じっくり読んでみたいです。
ルビィのぼうけん こんにちは!プログラミング
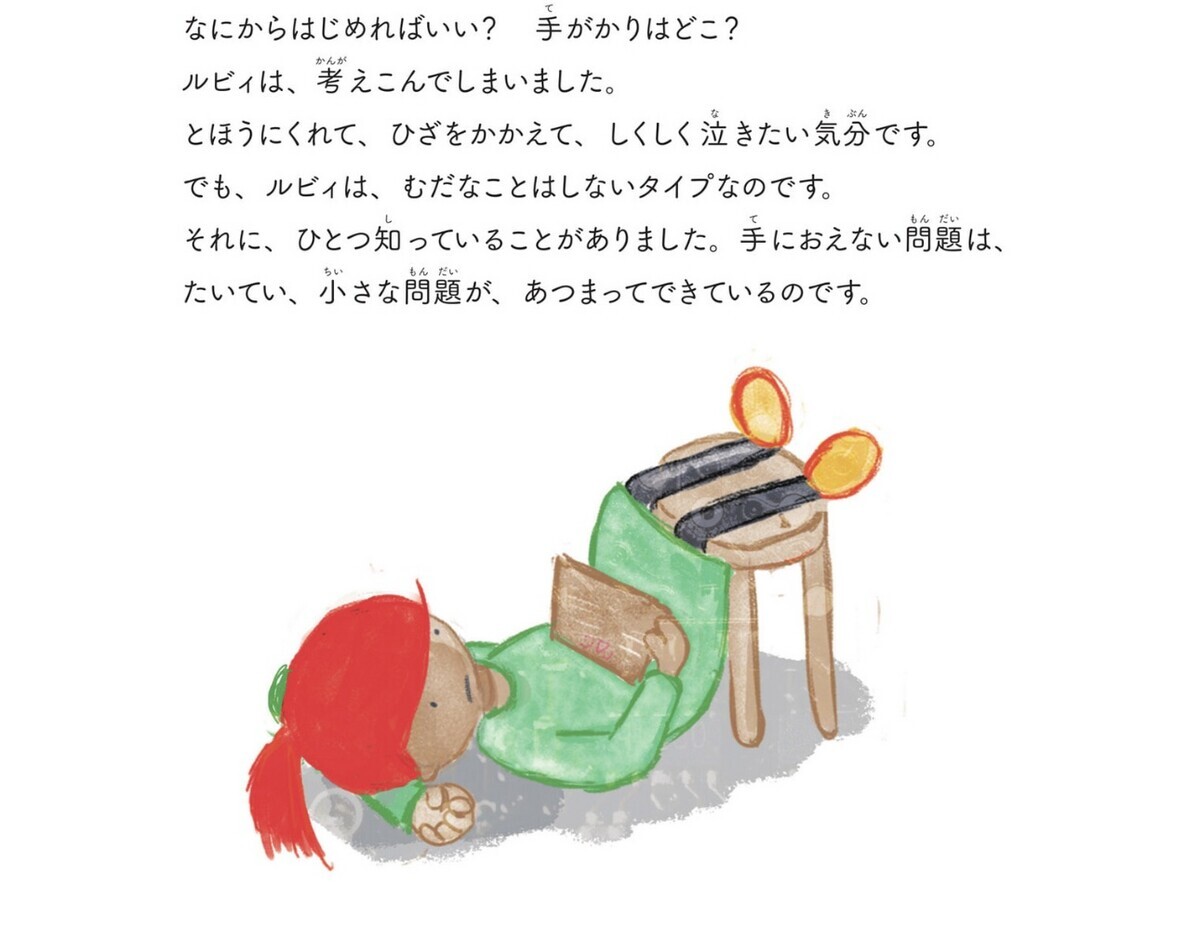
めったにないことなのですが、友人の勤務先で講演をしました。200人ぐらいの方が聞いてくださったようです。
新しい一歩を進むのに、躊躇している方に贈る言葉をと思い、ルビィちゃんの言葉を最後の締めにしました。(その関係で読み直しました。)やはり、名著。わたしも何度もルビィちゃんや、著者であるリンダに勇気づけられたことを思い出しました。
農業の絵本
仕事で、ビニールハウスの畑を借りて、障がい者の方々を雇用し、野菜を育ててもらっている。できた野菜は、社員が早い物順でいただけるという仕組み。
ただ、夏の間は、暑すぎて作業ができない日がある。去年は15日あった。昨年、始めて在宅勤務実施した。今年は、野菜づくりの本を読んで感想文を書いてもらおうということになり、何冊か図書館で選び、先日、興味が持てるか、農業を学ぶ助けになるか、レベル的に読み通すことができるかスタッフに見てもらった。持っていったものは大丈夫そうだったので、数冊会社で購入して貸出をすることになりそう。
読んでみて、農業の仕組みをコンパクトに絵本で学べるのは、楽しい体験でした。
以上、読んでいただきありがとうございました。
今月は、仕事関係で本を読むことが多かったので、3月はエンタメ的に読める本にも出会えるようにしようと思います!